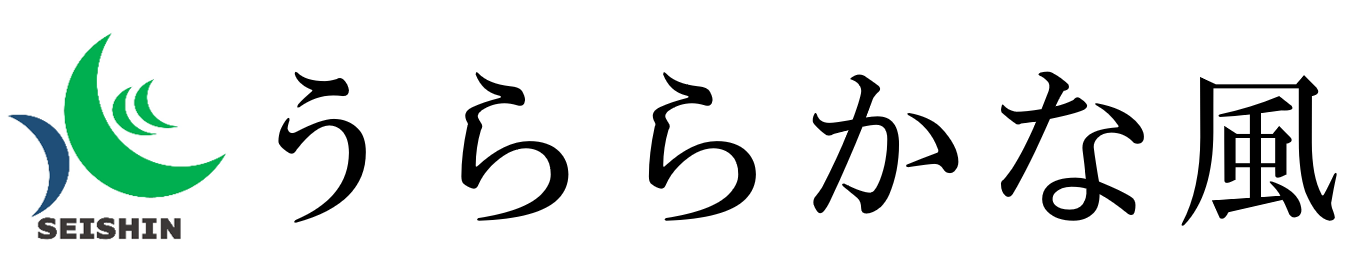「経営道」~形を超えて流れるぬくもり

山田無文老師は、著書『和顔』の中で、学問という「形」に囚われ、目の前の母の慈しみを見失った息子の寓話を引かれています。
『昔の笑い話に、都へ上って学問をしておる子供が帰ってくるというので、お母さんが喜んで宿場まで息子を迎えに行った。一緒に肩を並べて帰ろうと思って、家へ向かおうとしたら、息子が、「お母さん、どうぞ先へ行って下さい。私は『三尺下がって師の影を踏まず』と教わりましたが、親の影も先生の影と同じことです。ちょっと離れて歩いていただきたい」と、親と一緒に連れだって歩こうとしなかった。
家へ帰って母親が一所懸命に晩ご飯の仕度をしてやったら、じっとお膳を眺めていて、「割りめ正しからざれば食らわず」と習ったので、この人参や大根の切り目がよくないからいただきません」と箸をつけなかった。』
「そういう形にはまった杓子定規な道徳というものは、まことに困ったものであり、そういうふうに、どうかすると道徳が形にはまった死物になってしまうのであります。」
この言葉は、就労支援の現場で「一個入魂」を掲げる私の胸に、鋭く、深く突き刺さります。 私たちは、障がいを抱える仲間たちとともに、お客様の笑顔を願い、一つひとつのお弁当に心を込めています。しかし、経営者として「利益」という数字に向き合うとき、私の心にはいつしか執着の影が芽生えます。「もっと効率を上げなければ」「事業を存続させねば」……。その切迫した思いが、いつしか「正しい経営」という形に私を縛り付け、本来あったはずの純粋な願いを、どこか遠い「死物」へと変えてしまいそうになるのです。
利益を追うことは、仲間たちの生活を守るために不可欠なことです。けれど、数字という「形」に心が囚われるとき、私はお弁当の向こう側にいるお客様の顔も、ともに働く仲間の手のぬくもりも見失ってしまいます。
老師はこう説かれます。
「その臨機応変のはたらきというものはどこから出てくるかというと、何も思わんところから自然に出てくるのです。その、何も思わぬという純粋な気持ちをいつも失わないということが、一番大事なことであり、それが『信心』ということであります。」
「利益を出さねばならない」という不安も、「立派な経営者であらねば」という気負いも、一度すべて手放してみる。ただ、目の前にある人参の鮮やかさや立ち昇るごはんの湯気、仲間が一生懸命に盛り付ける仕草、そしてそれを受け取るお客様の空腹に思いを馳せてみる。
何も思わぬ、まっさらな心で「今」という瞬間に立ち返るとき、経営という義務は、再び「一個入魂」という生きた喜びへと通じていきます。利益とは、その純粋なはたらきが、世の中と響き合った結果として自然に巡ってくる「報い」に過ぎないのかもしれません。
迷い、志しが薄れそうになるたびに、私はこの「何も思わぬ純粋な気持ち」という原点に立ち戻ります。その葛藤の繰り返しこそが、私の「信心」であり、私たちの作るお弁当に、血の通った温かさを宿す唯一の道なのだと信じて。