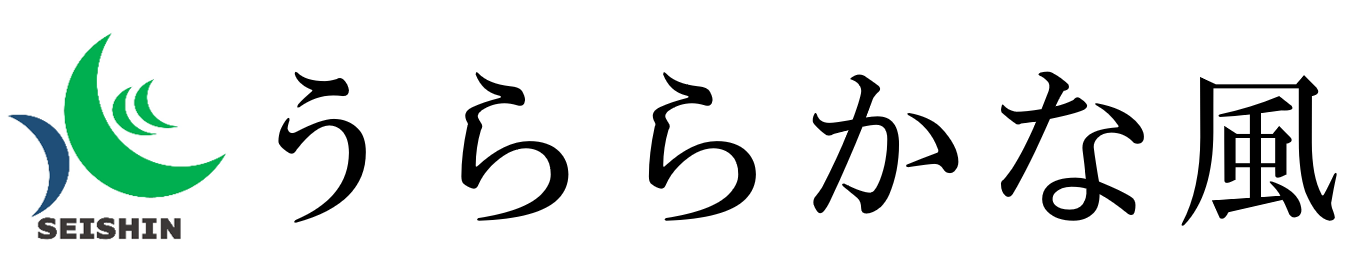命の花言葉~究極の「救護」

本日は、想定を遥かに超えるご注文を頂戴し、調理する方、盛り付ける方、配達する方、職員の皆さんにとってストレスフルな日になりました。何より、お届けが遅くなりましたお客様には、大変ご迷惑をお掛けしました。これもひとえに、私の見込みの甘さが要因でした。心よりお詫び申し上げます。弁当作りが予定通り進んでいない状況を把握した場合、配達先の分担を見直すなど適切な措置を講じる必要があります。今後はもっと早い段階で情報把握し、共有をし、手立てを講じることを心掛けていきます。
昨日11月10日の誕生花の一つは「ガマ」でした。ガマの花言葉には、「慈愛」とともに、「救護」があります。「救護」は困っている人を助け、命を守る行為を意味します。究極の献身を体現した一人の青年の感動的な物語がありました。戦後間もない昭和24年、長崎県の「打坂」という急勾配で起きた出来事です。
地元の乗合バスが、坂の途中でエンジン故障、ブレーキ不良、ギアも入らないという三重のトラブルに見舞われ、バスはコントロールを失い、ズルズルと後退し始めたのです。乗っていた方々のほとんどは、原爆症の治療に通う、お年寄りと子どもたちでした。自力で動くことが困難な人々にとって、逃げ出すことは事実上不可能だったのです。坂の下は、ガードレールのない崖。絶体絶命の状況でした。そのバスには、鬼塚道男さんという21歳の若い車掌が乗っていました。運転手の指示を受け、鬼塚さんは車止めとなるものを探して飛び降りますが、増していくバスの勢いを止めることはできません。崖までの距離は、もうわずか数メートル。全員が死を覚悟したその時、バスは奇跡的に止まりました。しかし、そこに鬼塚さんの姿はありませんでした。バスの後ろを見た運転手は、言葉を失います。そこには、自らの体を後車輪に投げ入れ、血まみれの車止めとなって、すでに息を引き取っていた鬼塚さんの無惨な姿があったのです。
彼は、乗客たちの命を自分が守り抜くという、究極の行動をとったのです。救われた乗客たちは、鬼塚さんの遺体を運びながら、口々にこう言いました。「この方は、仏さんか菩薩さんの生まれ変わりだ」と。彼の魂は、まさに、人々の悲しみや苦しみを和らげる「慈愛」に満ちていました。事故現場付近には、彼の供養のためにお地蔵が建てられ、70年余りたった今も、地域の人々による供養が続けられています。