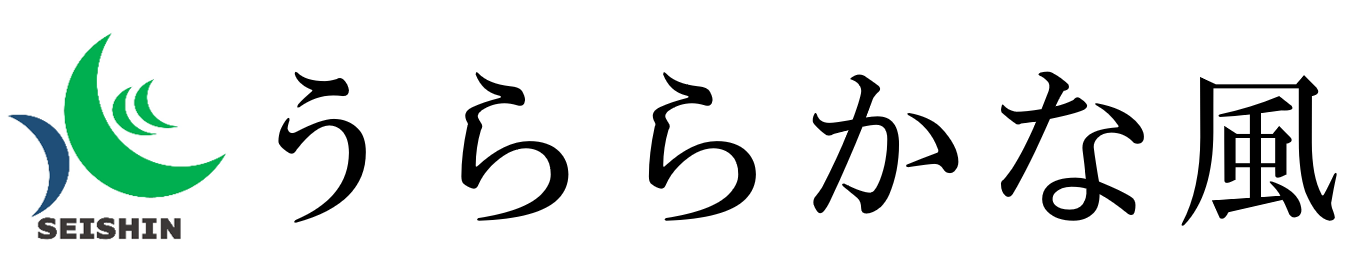他者の苦しみを測らない生き方

今朝、オリオン座が真っ暗な夜空に浮かび上がって見えました。澄んだ空気の寒い日には、夏には見つけられなかった小さな星を見つけることができます。今日は二十四節気の一つ「霜降(そうこう)」、露が冷気によって霜となって降り始める頃という意味です。10度を下回る気温ではないため、霜が降りることはありませんが、まだ体が慣れていないため寒く感じます。
詩人、坂村真民先生の詩に、このような一節があります。
“苦が その人を 鍛えあげる 磨き上げる 本物にする”
私たちは、困難や苦しみに耐えることが、自分自身を成長させ、本物にしてくれると知っています。苦労を乗り越えてこそ得られる力というものは、確かにあります。しかし、この「苦しみ」をどう捉えるかという点に、大きな落とし穴があります。時に、私たちは無意識のうちに、「自分が耐えた苦しみ」を基準にして、他人、特に若い世代の苦労を測ってしまうことがあります。
「自分たちはこんなに苦労したのに、今の人は甘い、苦労が足りない」
自分が体験したのと同じような厳しさに耐えてもらいたいと思うものです。ですが、その考えには、実は「慢心」が既に潜んでいる可能性があります。「自分はこんな苦しみに耐えたのだ」という思いが、いつの間にか優越感となり、他者の苦しみを軽視してしまう原因になりかねません。これは、仏教でいう「おごり」です。この世に生きることは、すべての人にとって「苦しみ」を伴うということです。仏教の教えでは「一切皆苦(いっさいかいく)」と説かれています。私たちは、どんな環境にあっても、誰もが苦しみを抱えて生きています。若者は若いなりに、外から見れば苦労がないように見えても、彼らには彼ら特有の、その境遇でないと分からない悩みや苦しみが必ずあります。そのことを理解せず、「自分だけが特別の苦労をした」と考えることは、慢心にほかなりません。大切なのは、そのように相手の苦しみを認め、受け入れる「慈悲のまなざし」を持つことです。私たち自身が、自分だけの苦労を基準にする慢心から離れ、お互いの苦しみを共にして、一緒に成長していくこと。これが、真の修行であり、豊かな人間関係を築く道ではないでしょうか。