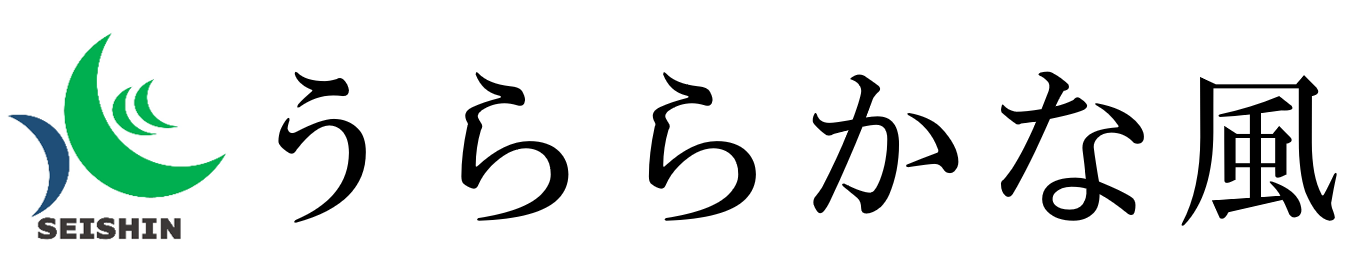「花火は好きになれない」

ある雑誌で、戦争を体験された方の「花火は好きになれない」という言葉に出会いました。その言葉の出典は、作家の半藤一利さんの著書『戦争というもの』でした。巻頭には、「人間の眼は、歴史を学ぶことではじめて開くものである」という言葉があります。私たちに、歴史から目を背けるなと強く訴えかけているのです。
まえがきには、太平洋戦争の残虐さが記されています。半藤さんは言います。「その戦争の残虐さ、空しさに、どんな衝撃を受けたとしても、受けすぎるということはありません」、「破壊力の無制限の大きさ、非情さについて、いくらでも語りつづけたほうがいい」と。日本全土が焼け野原となり、万骨が空しく枯れたのち、昭和20年8月15日に戦争は終わりました。半藤さんは、こうも警告しています。「戦争によって人間は被害者になるが、同時に傍観者にもなりうるし、加害者になることもある。そこに戦争の恐ろしさがあるのです」と。
この本の解説を書かれたのは、半藤さんの奥様です。奥様は、新潟県の長岡で昭和20年8月1日の大空襲を体験されました。奥様は、その夜の光景を「地上からはメラメラと燃えたつ巨大な炎の柱が天を射るようにそびえ立ち、闇夜を真っ赤に染め上げた」と記しています。だから、長岡まつりの花火を見るたびに、空襲の夜の「悲しい美しさ」を思い起こしてしまうのだと。そして、「亡き夫も花火は大嫌いでした」と結ばれています。同じ花火を見ても、きれいだと見る人もいれば、空襲の炎や音を思い起こす人もいるのです。
私は、この辛い記憶を持つ人がいるからこそ、平和が保たれているように感じます。「天災と違って、戦争は人間の叡智で防げるものです。戦争は悪であると、私は心から憎んでいます。あの恐ろしい体験をする者も、それを目撃する者も、二度と、決して生みだしてはならない。それが私たち戦争体験者の願いなのです」と。半藤一利さんご夫妻が、生涯を通して語り続けた戦争の真実と平和への強い願い。私たちは、この言葉を未来へとしっかりと受け継ぎ、歴史を学ぶ眼を閉じてはならないのです。