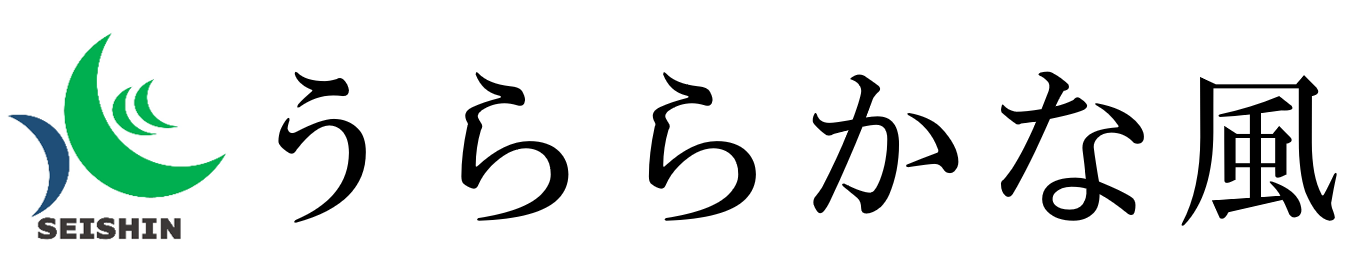鈍刀を磨く

9月に月刊誌「ルーツ」の取材で、タレントの布川敏和さんがわざわざうららかな風にお越しいただき、インタビューを受けました。その取材記事が掲載されましたので、お時間がある時にご覧くださいませ。
お待たせ致しました。2025年1月分の献立表が完成いたしました。気になるメニューが盛りだくさんです。「一個入魂」。利用者様、スタッフが一丸となって、お客様のために、心を込めてお作りしております。多くの皆さまの目に留まり、ご注文を頂くことができればこの上なく幸せに存じます。どうぞ宜しくお願い致します。
「のこぎり職人の話」
ノコギリの目立ての職人であります。十三歳からノコギリ製造の鍛冶屋に丁稚奉公に入り一生懸命勤めて、若くして認められてゆくのですが、不注意から、全身に火花を浴びて片目を失明してしまいました。片目では遠近感が得られませんので、職人としては致命傷です。しかし、その職人はあきらめずに人の何倍も努力したのでした。
親方から、自分には目は二つある、お前は一つしかない、だから教えることはなにもない、人の何倍もやるだけやれとだけ言われました。その言葉通り、血のにじむような努力を重ねた結果、ようやく一人前になれたのです。ところが、目が不自由だということで、まともに仕事ができないと思われて全くお客が来ませんでした。
たまたま、その地方で一番腕の立つ大工の親方が急な仕事で、ノコギリの目立てを頼みたいと思ったけれどもどこの職人も手いっぱいで、すぐにできない。そこで、その職人のところに注文がまわってきました。
「まともにできないらしいと噂をされているけれども普通に切れるくらいにしてくれたらいい」と注文されました。これほどの屈辱はなかったと後に語っています。しかし、大工の職人は、一度そのノコギリをひいてみて目立ての名人であると分かりました。その後は、すべてのノコギリの目立てを頼まれるようになりました。
ノコギリ職人の晩年のこと、御孫さんとお風呂に入ると、その職人の全身が古傷だらけだったそうです。毎朝、まだ暗い中、林の中を体中、傷だらけになりながら、枝をよける訓練をして遠近感を養う努力をしていたのです。何十年も苦労を重ねて、幾多のハンディキャップを乗り越えて立派な職人になったのです。
この話を読んで私は、坂村真民先生の「鈍刀を磨く」という詩を思い起こしました。
鈍刀をいくら磨いても
無駄なことだというが
何もそんなことばに
耳を貸す必要はない
せっせと磨くのだ
刀は光らないかもしれないが
磨く本人が変わってくる
つまり刀がすまぬすまぬと言いながら
磨く本人を 光るものにしてくれるのだ
そこが甚深微妙(じんしんみみょう)の世界だ
だからせっせと磨くのだ
私は、日々そのような努力を積み重ねているだろうかと、恥ずかしく思いました。