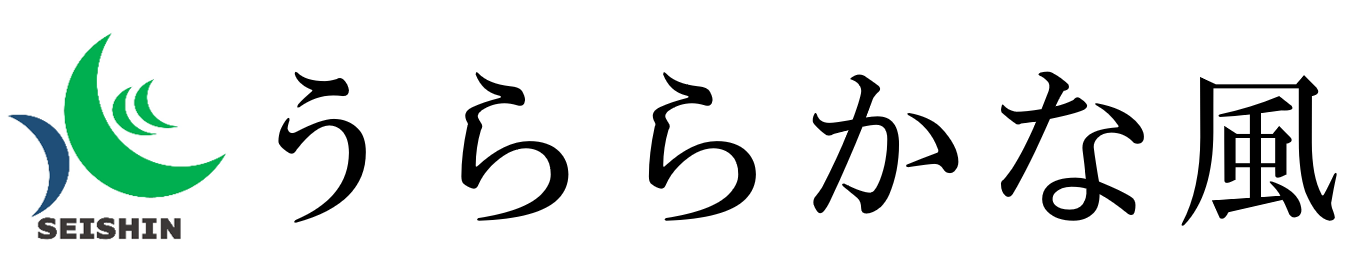止まった時計が動くとき ― 阪神・淡路大震災、31年目の祈り

体調を崩して欠席される利用者様が増えております。インフルエンザのB型が流行っているようです。マスク、手洗い、うがい。コロナ時代には当たり前だった習慣を思い起こして感染予防に努めてください。
31年前の平成7年(1995年)1月17日、午前5時46分。 あの日、世界は一瞬にして姿を変えました。阪神・淡路大震災。マグニチュード7.3、最大震度7。戦後初めて大都市を襲った直下型地震は、6,434人の命と、数えきれない人々の日常を無慈悲に奪い去りました。
兵庫県川西市の向邦男さんは、今年、妻の千鶴さん、そして孫の睦さんとともに、神戸・東遊園地の追悼の場に立っていました。 「31年は長く、少しずつ前進した時間やった」 。あの日、向さんが駆けつけた神戸市兵庫区の住宅は、猛烈な炎に包まれていました。父・昇さんと母・二三子さんは、その炎にのまれ、後に見つかったのは遺骨だけでした。 変わり果てた故郷。絶望の淵で出会った一人の男性の姿を、向さんは忘れることができません。その手には、生き埋めになった妻を助け出せず、引きちぎれるほどに握りしめた「彼女の髪の毛」が残されていました。そのあまりの残酷さに、向さんは長く、震災と向き合うことができませんでした。初めて追悼の場に足を運ぶことができたのは、あの日から約20年が過ぎた頃。きっかけは、当時小学生だった孫の睦さんに「あの日のこと」を語り始めたことでした。 痛みを言葉にすること。それが、止まっていた時計の針を動かしたのです。
東日本大震災、能登半島地震。自然の猛威の前に人間がいかに無力であるかを、何度も突きつけられてきました。 災害は誰のせいでもありません。しかし、備えを怠った結果として失われる命があるのなら、それは私たちが向き合わなければならない「責任」です。
「ここなら大丈夫」という安全神話は、どこにも存在しません。自然災害は抗うことができません。けれど、私たちは「準備」をすることで、その悲しみを減らすことができます。あの日、髪の毛を握りしめて泣いた人の絶望を繰り返さないために、向さんが31年かけて辿り着いた祈りを、明日を守る強さに変えていきましょう。