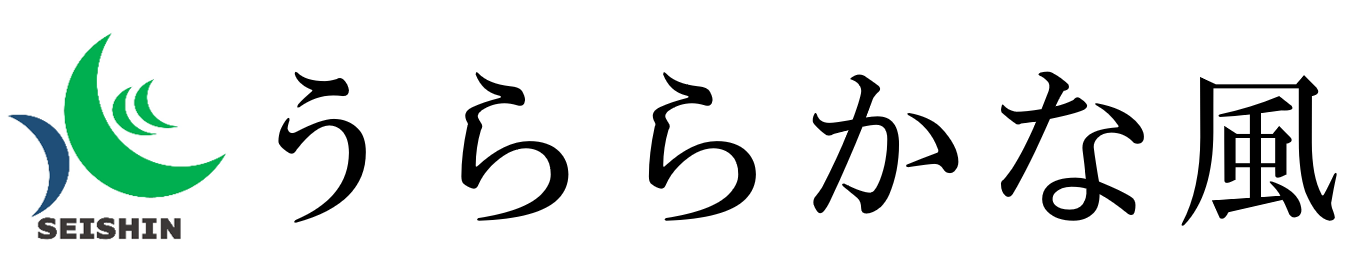幸せを呼ぶ循環~知恩なくして報恩なし

おはようございます。昨日11月3日は「文化の日」でした。昭和21年、日本国憲法が公布されたことを記念して、昭和23年に制定された国民の祝日です。「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としているそうです。かの大戦から今日まで80年余り経ちました。日本は憲法第九条で「戦争の放棄」を掲げ、自衛のための必要最小限の武力しか持たない専守防衛を基本としており、直接的に他国との間で大規模な戦争に巻き込まれることはありませんでした。戦火のない平和な日本がいつまでも続くことを願ってなりません。
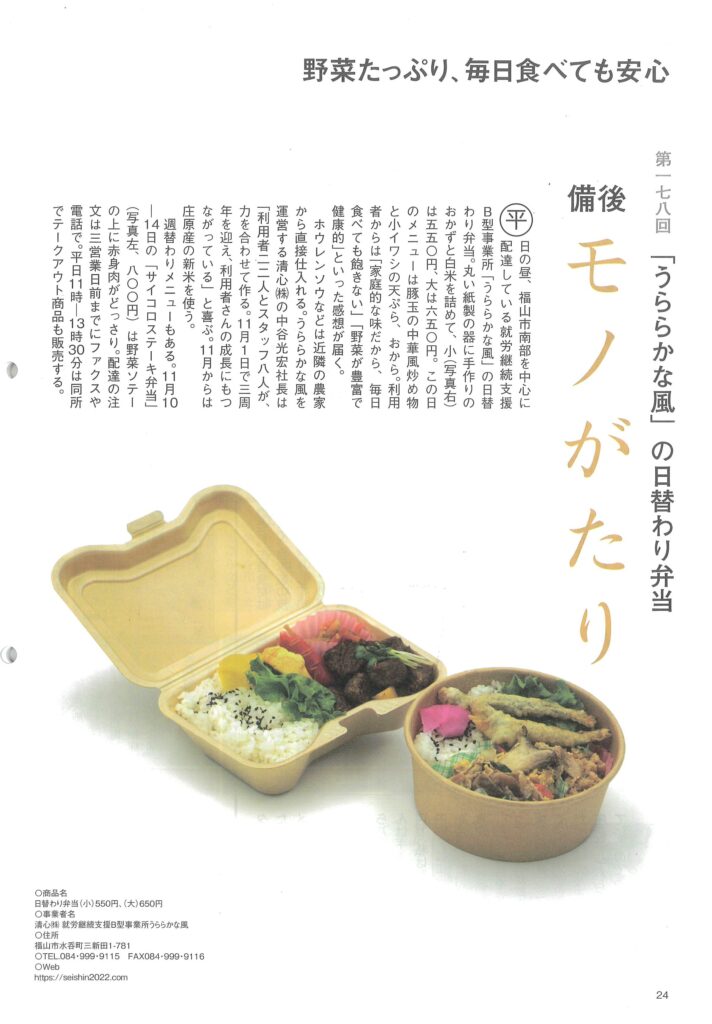
普段口にする「ありがとう」という言葉。この感謝の心は「恩を知る」ことから始まります。紀元前三世紀、古代インドに君臨したアショーカ王は、その勅令の中で、非常に重い言葉を残しています。どんなに広大な布施をなしたとしても「克己(こっき)、心の清らかさ、報恩、誠の信」という四つの精神がなければその人は賤しい人である、と。
この教えに注目された仏教学者の中村元博士は、アショーカ王が「一切の人間は相互に扶助され、互いに恩を受けているという道理」を深く確信していたと解説されています。国王でさえ生きとし生けるものから恩を受けている。であるならば、政治とは、この恩に報いる報恩の行でなければならないのです。真の価値とは、外面的な行為や権力ではなく、その根底にある知恩と報恩の精神性にあることが、ここで明らかになります。では、この恩を知るという「感謝」の心は、どのようなものなのでしょうか。『ブッダのことば』によれば、「感謝」とは、「他人から為されたことを感じ知る」ことであり、「知恩」とも訳されます。この知恩の心は、精神的な喜びを与えあう人類共通の財産です。日本人は「ありがとう」、朝鮮の人は「カムサ」、ベトナムの人は「カンノン(感恩)」と言うように、言葉は違えど、その相互扶助の精神は一つなのです。
「恩を知ってこそ、恩に報いることも出来る」のです。知恩なくして報恩なし。私たちが知恵の光を求めるブッダの教えの中には、「こよなき幸せ」を構成する要素として、「尊敬」と「謙遜」と「満足」と、そして「感謝」と「教えを聞くこと」が挙げられています。知恩の精神は謙虚さをもたらし、他者への報恩へとつながります。この知恩・報恩の循環こそが、私たち一人ひとりを、物質的な豊かさだけではない、深いこよなき幸せへと導いてくれるのです。