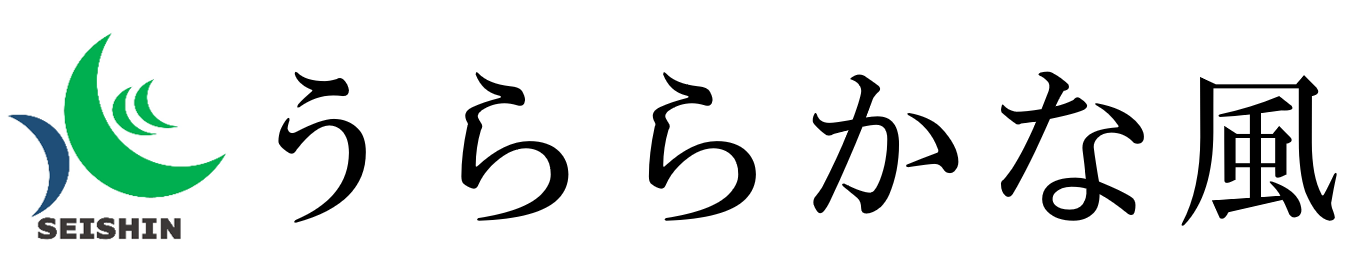「花」への希求と、消えない被爆の記憶

11月13日は詩人・谷川俊太郎さんの命日。詩集『二十億光年の孤独』を発表して以来、80冊以上の詩集を発表されました。谷川さんは1931年生まれで、太平洋戦争末期の14歳のとき、東京大空襲を体験しています。戦争の原因は個人の中にある衝動が組織の中で結びつくことにあると考え、「戦争はなくならない」という現実認識を持ちつつも、平和への希求を作品で表現し続けました。1960年、原水爆禁止世界大会に寄せられた詩の冒頭は、時代を超えて私たちの心に響きます。
「原爆をつくるな つくるなら 花をつくれ」
このフレーズは、各地の原水禁運動の合言葉となり、看板が設置されるなど、反核の意思を象徴する言葉となりました。中国新聞「こだま」欄に胸が苦しくなるような被爆者の体験談が掲載されておりました。ぜひご一読ください。
--
『治療奉仕』安芸高田市 浜田恵知子さん(95歳)
広島市に原爆が落とされ て数日後、女学生だった私は学徒動員で、市内にある国民学校に設けられた救護 所に行き、やけどを負った人たちの治療奉仕をした。窓のない長い校舎に寝かされた、大勢のさまざまな年齢の被爆者を治療する軍医を手伝った。熱線で焼けて剥げ、だらりと下がった皮膚を軍医が切ると、その患部に私が赤チンを塗り油紙を貼るのだ。
痛さのあまり泣き叫ぶ被爆者の姿を初めて目の当たりにした日、私は気絶してしまい校舎の隅に寝かされていた。どのくらい時間がたっただろうか、起き出してみると軍医が遠くの方で、1人で手当てをしておられた。私は軍医に近づき再び手伝いを始めた。校舎の外をみると、男たちが地面を長細く掘って亡くなられた人たちを埋めていた。その骨はどうなっているのだろうか。
100歳近くまで生きた今になっても、布団に入り目を閉じたら、あの時の様子が脳裏に浮かぶ。鋭い刃で腹がえぐられるような苦しみにさいなまれる。眠れぬまま、入所する高齢者施設の窓から見える星空に、かなたにそびえる山々に、いつまでも静かに手を合わせる。
「安らかにお眠りください」と。