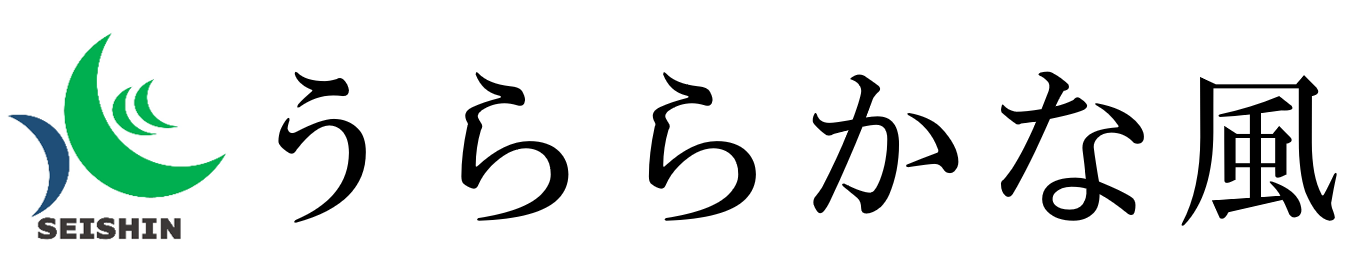命尽きるまで孤児たちのために命を捧げよう

広島は79回目の原爆の日を迎えました。たった一発の爆弾が街を破壊し、子どもを含む14万人という大勢の市民の命を無差別に奪いました。過ちを繰り返してはなりません。79年前のあの日を世界は忘れてはなりません。今日は、みなさん一人一人が、亡くなられた方々への鎮魂と、恒久平和を誓う日にしましょう。
8月1日号のビジネス情報『あの人のおすすめランチ』のコーナーで、オーザック岡崎副社長様がうららかな風を紹介してくださいました。岡崎副社長様は、お弁当のご注文をいただくだけでなく、うららかの利用者様のことをいつもあたたかく見守り、応援してくださいます。お弁当をお届けするために玄関に入ると、どんなに忙しくても職員の皆さんが笑顔で出迎えてくださるんです。やさしさに溢れているんです。それは利用者様も敏感に感じ取っており、「オーザックの配達ある?」、「副社長さん、おってかな?」と配達を楽しみにしています。副社長様のご期待に沿えるよう、もっともっとおいしいお弁当を作ります!

『孤児たちのために生き、孤児たちのために死ぬ 田内千鶴子』
母が他界して今年で40年の歳月が流れました。最近、韓国のテレビ局が母のドキュメンタリーを制作したり、古里の高知で顕彰の動きが盛り上がったり、その足跡が広く紹介される機会も増えてきました。日韓両国の人々が過去の不幸な歴史を乗り超え、人間愛や平和について考えるよすがとなれば、天国の母も本望だと思います。母の名は田内千鶴子(韓国名・尹鶴子)。戦後の韓国で孤児院を運営し、3000人の孤児を育てあげ、皆から「オモニ」(お母さん)と慕われ続けました。
日本人に対する迫害が最も激しかった時代、反日感情と貧しさに耐えつつ一人で施設を切り盛りする苦労は筆舌に尽くしがたいものがあったことでしょうが、間近にいた私は、母が泣き言や愚痴を言う姿を一度も見たことがありません。逆にどのような状況でも、信仰に裏打ちされた献身的努力を続け、孤児の幸せのためだけに人生を捧げ尽くした人でした。昭和43年に56歳で亡くなった時、市民葬に3万人が参列しました。清貧に生きた無名の日本人の死を、これほど多くの人が悼み、号泣した例は韓国の歴史にあったでしょうか。
母は大正元年に高知県で生まれ、幼少期に朝鮮総督府に勤めていた父親に呼ばれて韓国に移ります。そして26歳の時、ボロボロの身なりで孤児の救済に当たっていた韓国人キリスト教伝道師の父と出会い結婚。韓国南西部・木浦市内にある、孤児院とは名ばかりの廃屋同然の木浦共生園で、4、50人の孤児と寝起きを共にしながらの新婚生活をスタートします。しかし、貧しくも希望に燃えた二人三脚の日々は長くは続きませんでした。やがて訪れる朝鮮戦争の最中、父が食料調達に行ったまま消息を絶ってしまったからです。以来、母は父の帰りを夢見ながら、一人で共生園の運営を続けます。父が帰るまでは何としても孤児院を守るという一念だったといいます。
動乱で親を亡くした孤児の数は増え続ける一方で、運営は困難を極めました。建物の拡充も必要でしたが、差し当たり必要なのはきょう口にする食料でした。母自らリヤカーを引いて残飯を集め、役所を訪れては援助を訴えました。まるで物乞いです。しかし母は周囲の雑音を意に介することなく、たどたどしい韓国語を話しながら小さな体で食料や資金の確保に走り回り、孤児を育てていくのです。病気の子は夜を徹して看病し、ひもじい思いをする子には自分の食事を分け与えました。一緒に遊び、歌い、抱擁し、そして祈り、精いっぱいの愛情を注ぎました。いつも温かい視線を注いでくれる母を、孤児たちはいつの間にか皆本当の母親のように慕うようになりました。戦後間もない頃、凶器を手にした村人が突然、共生園を訪れ、日本人である母の命を奪おうとしたことがあります。その時、孤児たちは「オモニに手を出させるものか」と一斉に母を取り囲んだのです。村人は無言のまま立ち去りましたが、母は後にこの時を振り返り、「孤児たちが守ってくれた命。ならば、死ぬまで孤児のために命を捧げようと決意した」と話していました。その言葉どおり母は終生、この誓いを貫き通したのです―――。